暗闇散歩 | DIALOG IN THE DARK
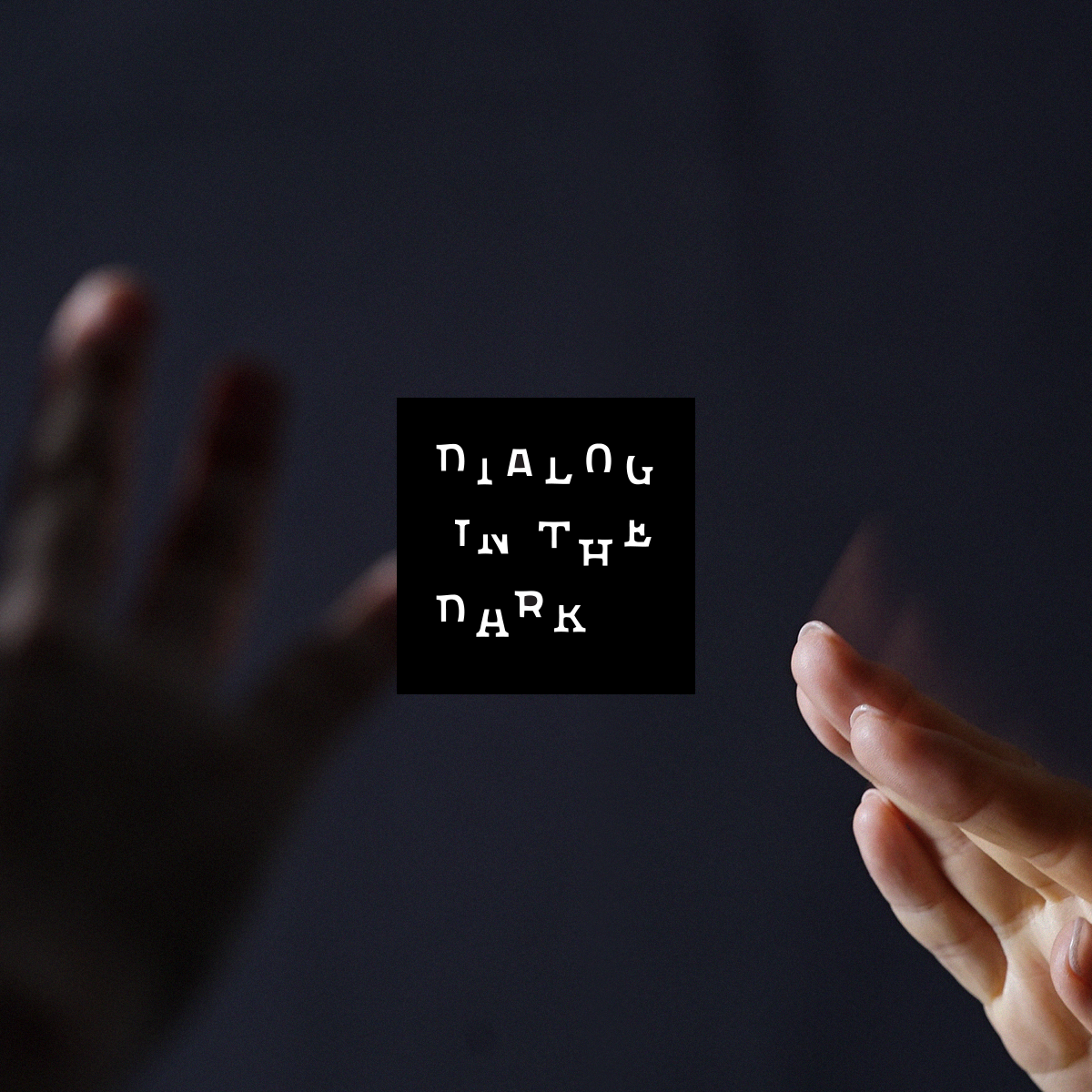
写真の撮影法に長時間露光という手法がある。
シャッターを開いたまま数分、数十分と露光すれば
辺りがどんなに暗くても微量の光を集め続け、写真として焼き付けることができる。
そう、微かな光さえあればー
ダイアログ・イン・ザ・ダークとは、
「照度ゼロ」の完全な暗闇空間の中で、聴覚や触覚など視覚以外の感覚を使って
日常生活のさまざまなシーンを体験するエンターテイメント。
個人的には二度目の参加。
今回の会場はコンクリートで固められた外苑前のとあるビルの地下。
数年前、この場所はブラジル系のカジュアルなレストランが入っていて、
僕はたまにランチバイキングを食べに来ていた。
そこではラモス瑠偉がよく現れサッカー談議に花を咲かせていたが、
いつの間にか闇に変わっていた。
初対面同士の8人が一組のグループとして体験する。
会場内を案内してくれるのは視覚障害者のちくわ君(ニックネーム)。
彼がアテンドとしてゴールまで安全に牽引してくれるのだ。
彼の声を頼りに進むしか方法はない。
一歩闇に足を踏み入れた瞬間、気づけば
「障害者」という概念が消滅し、むしろ立場は逆転する。
一切の光が遮断された世界。
形、色、質感、すべての視覚的情報が身を隠し、次元がグニャリと歪む錯覚をおぼえる。
文字通りの暗黒。
研ぎ澄まされる聴覚。
もはや足の裏の感覚と、恐る恐る手を伸ばしモノに触れる感触で過去の記憶を頼りに
自らが偶像を作りだし、経験を組み立てていくしかない。
(ネタバレになるので書かないけれど、暗闇の中には様々なモノが用意されている。)
物や人との距離感はもちろん、初対面だった参加者との関係性すら一瞬にして失われ平均化される。
僕は少しの恐怖を感じた。
しかし汗を掻いた手の平すらこの闇の中では目視することが許されない。
光は時に人工的なものとして捉えられる。
では逆に暗闇は自然な状態だろうか。
例えば蝋燭の火のみで照らされた部屋は、コンビニエンスストアよりは自然な状態かもしれない。
しかしこの暗闇はどう考慮しても自然な状態とは言えない。
<光量ゼロ>の暗闇世界というのはある種究極の人工物かもしれない

8人一組のグループとしてゆっくり進む。
必然的にコミュニケーションを取らざるを得なくなる。
大事なのは声だ。
相手から発せられる声の位置で距離感をつかむ。
自分の発する声で自らの存在を理解してもらう。
自分はここにいる
そう言い続けないと闇に侵食され存在が消滅しそうだった。
だんだんその環境に慣れてくると、そのグループ内で自分という存在をどう認識してもらうか、を
無意識に考えるようになった。
ある人は何事も率先して声を出し、ある人はフォローに回る。
ある人は好奇心旺盛に新しい道を探し出そうとし、ある人は常に場を和ませようとする。
時間感覚が失われてから約90分が経過し、暗闇散歩が終了。
濃密な時間だった。
出口に用意されたアンケートコーナー。
薄明りが灯されたテーブルライトがじんわり網膜を刺激する。
僕はアンケートに「もっともっと長く、できれば丸一日居たかった」と書いた。
感覚の一部を損なわれる体験はあまりに新鮮で、親密な闇をなぜか愛おしくさえ感じた。
普段無意識に意識させられている焦燥感みたいなものが、
外部の圧倒的な力によって閉ざされることに僕は安堵していたのかもしれない。
人は人を区別する。
見た目や職業や肩書き、組織や人間関係としての役割、立場。
しかしそれらが強制的にリセットされ、個として他人と(自分とも)向き合わされる。
一瞬孤独を感じるが、逆説的に人との関わり合いの中で生きている事実を実感する。
いかに視覚というものに物事の本質が覆い隠されているか、
価値観を左右されているか。
あらためて考えさせられた。
そしてなにより光があることのありがたみを実感した。
日々の忙しさで当たり前の幸せが見えなくなってしまうから、
常に自覚していたい。そう思った。